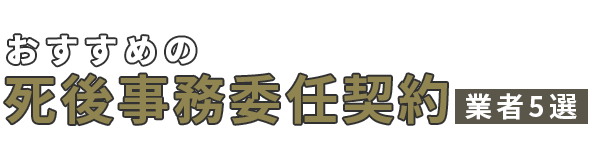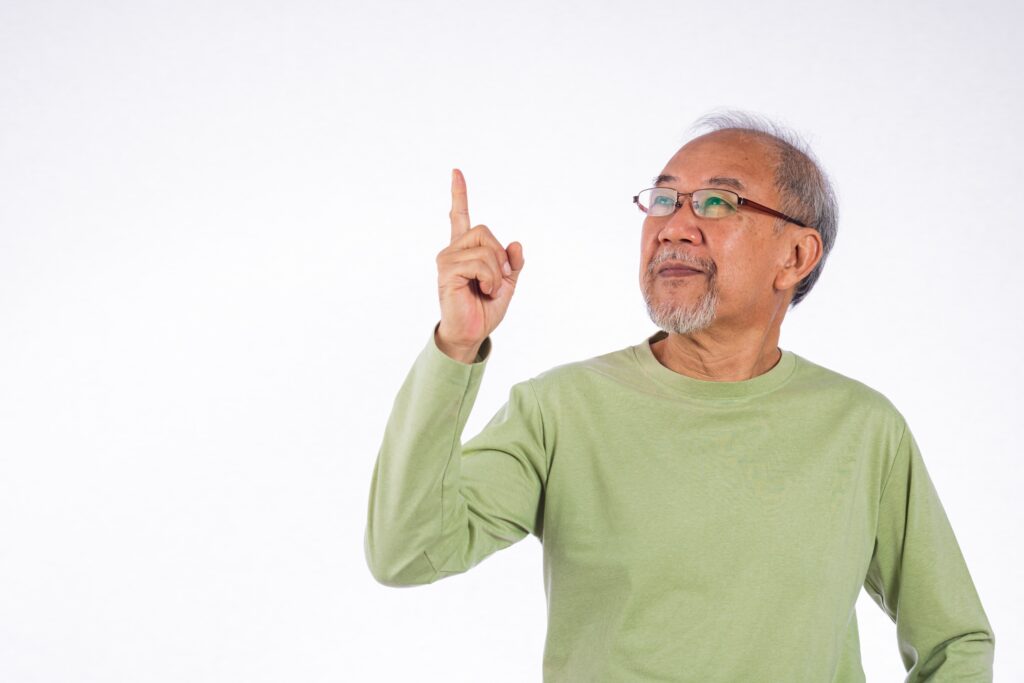
近年、家族や親族とのつながりが希薄になり、おひとりさまとして自分らしく生きる人が増えています。一方で、もしものときの葬儀や遺品整理、役所への届出などをどうするのか不安になる方も多いでしょう。そこで実施したいのが「終活」です。この記事では、身寄りのない方が終活すべき理由を詳しく解説するので参考にしてください。
おひとりさまが終活を行うべき理由
現代では、生涯を独身で過ごす人や子どもがいない人が増え「おひとりさま」と呼ばれる生き方もめずらしくなくなりました。しかし、老後や死後のことを誰かに任せられないことを、どこかで不安を感じるのではないでしょうか。おひとりさまこそ終活によって自分の考えをまとめ、意思表示することが重要です。孤独死のリスクを減らす
身寄りがない人が誰にも気づかれず、数日後や数週間後に発見される事件が発生しています。終活を通じて自分の生活状況を整理し、信頼できる第三者や専門機関に託すことで、孤独死の可能性を大幅に削減できます。保証人を確保できない
通常、病院への入院や介護施設への入所時には、保証人や身元引受人の署名を求められるのが一般的です。しかし、家族がいない場合、保証人や身元引受人を確保できない恐れがあります。この問題を解決するためには「身元保証サービス」や「死後事務委任契約」を利用し、入院・入所の手続きから退院後の片付けなどを代行してもらう必要があります。相続でトラブルが起こる
終活の一環として遺言書を作成していない場合、法定相続人が自動的に遺産を受け継ぐことになります。自分の意思と異なる人に財産が渡るのを防ぐために遺言を作成し、信頼できる人や団体に託すことが不可欠です。近所トラブルを防ぐ
終活せずに亡くなった場合、遺体の発見や手続きの負担が近隣住民や自治体におよぶことがあります。孤独死による悪臭や害虫の発生など、避けられないこともあります。さらに、病院で亡くなった場合でも、遺体の引き取り手がいないと自治体が対応することになり、職員や関係機関の負担になってしまいます。また、仮にお墓を所有していても納骨されないケースもあります。おひとりさまが行うべき終活の内容
終活の内容は多岐にわたります。ここでは、身寄りがない方が検討しておきたい終活の内容を押さえておきましょう。死後事務委任契約を結ぶ
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種の事務手続きを、信頼できる第三者に任せるための契約です。人が亡くなると、葬儀や火葬の手配、納骨や埋葬、病院や介護施設への支払い、相続、公共料金の支払いや解約、自宅の片付けなど、多くの手続きが必要になります。家族がいればこうした作業を担ってくれますが、身寄りのない方は実施できません。また、ご家族がいる方でも、遠方に住んでいたり疎遠だったりする場合、これらの作業はかなりの負担になります。そのため、死後事務委任契約を結んでおくことで、これらの手続きを確実に遂行できます。
契約の相手は誰でも選べますが、実務を安心して任せられる司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。専門家に依頼すれば、法的に有効な契約内容を整えられるほか、死後のトラブルも防ぎやすくなります。
エンディングノートの作成
死後事務委任契約とあわせて取り組みたいのが、エンディングノートの作成です。エンディングノートは、自分の人生や思い、葬儀の希望、連絡してほしい人の情報などを書き残すノートで、法的効力はないものの、遺された人にとって大切な指針になります。記載するのは、書店などで専用のノートを購入してもいいですし、市販のノートでも構いません。葬儀の希望、医療方針、資産や保険の情報、ペットの世話など、自分に関する情報を整理しておくことで、死後事務委任契約を結ぶ相手にも伝わりやすくなります。
見守りサービスの活用
次に考えたいのは、見守りサービスの利用です。おひとりさまの場合、急病や事故が起きても周囲に気づかれにくく、孤独死のリスクが高まります。見守りサービスを導入すれば、異変を早期に発見してもらいやすくなります。身元保証サービスの活用
病院への入院や介護施設への入所では、保証人が必要となるケースが多くあります。保証人を代行してくれるのが身元保証サービスです。契約内容によっては、日常生活の支援や金銭管理を含めたサポートを受けられる場合もあります。終活を始めるタイミングはいつ?
終活を始めるタイミングに明確な決まりはありません。しかし、体力がなくなると検討・行動しづらくなるため、元気で心身ともに余裕のあるうちに取り組むとよいでしょう。一般的には、仕事や子育てがひと段落し、自分自身のこれからを見つめ直す60代中盤から70代にかけて開始する人が多いとされています。時間に追われず、気持ちにも余裕をもって取り組めるため、納得のいく終活ができるでしょう。