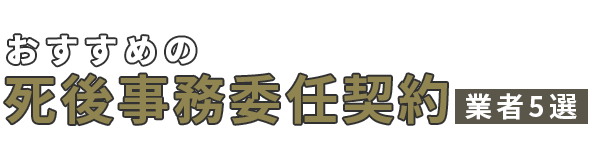遺品整理と生前整理は、どちらも身の回りの物を整理する作業ですが、実施するタイミングや目的に大きな違いがあります。近年では、残された家族の負担を軽減するため、生前に遺品整理業者と契約を結ぶケースも増加中です。本記事では、両者の具体的な違いから、生前に遺品整理を依頼する方法、整理した品物の処分方法を解説していきます。
遺品整理と生前整理の違い
遺品整理と生前整理の最も大きな違いは、実施するタイミングにあります。遺品整理は故人が亡くなった後に遺族が行う作業であり、生前整理は本人が存命中に自身で行う作業です。遺品整理では、故人の所有物すべてが対象となり、貴重品の捜索から不用品の処分、部屋の原状回復まで幅広い作業が含まれます。一方で生前整理は、本人の意思で必要な物と不要な物を選別し、財産目録の作成や相続に関する準備も同時に進めることが可能です。作業の主体も異なり、遺品整理は遺族や専門業者が中心となって進めますが、生前整理では本人が主導権を持って進められるため、思い出の品の取り扱いや処分方法について自分の意向を反映させやすいという特徴があります。
また、精神的な負担にも違いが生じます。遺品整理では、悲しみの中で作業を進める必要があり、故人の思い出と向き合いながらの作業は遺族にとって大きな精神的負担となることが少なくありません。これに対して生前整理は、自分のペースで計画的に進められるため、精神的な余裕を持って取り組めます。
費用面でも差があり、遺品整理は急を要することが多く、短期間で完了させる必要があるため、業者への依頼費用が高額になりがちです。しかし生前整理なら、時間をかけて少しずつ進められるので、費用を抑えることができるでしょう。さらに、法的な手続きの面でも違いがあり、遺品整理では相続放棄の期限や相続税の申告期といった時間的制約が存在します。
生前に死後の遺品整理を依頼する方法
生前に自身の死後の遺品整理を依頼する方法として、最も確実なのは遺品整理業者との生前予約契約を結ぶことです。この契約では、依頼者が亡くなった際の連絡方法、整理の範囲、処分方法などを詳細に取り決めます。契約時には、業者の信頼性を確認することが重要であり、一般社団法人遺品整理士認定協会の認定を受けた遺品整理士が在籍している業者を選ぶと安心でしょう。契約内容には、整理作業の具体的な範囲、貴重品や思い出の品の取り扱い方法、処分品の分別方法、作業完了後の清掃範囲などを明記します。また、費用の支払い方法も重要なポイントとなり、信託銀行を利用した遺言信託や、死後事務委任契約を活用する方法があります。
死後事務委任契約は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することで、遺品整理だけでなく葬儀の手配や各種手続きも含めて委任できる制度です。契約金額は、1LDKで10万円から30万円、2LDKで15万円から50万円程度が相場となっています。
ただし、特殊清掃が必要な場合や、エレベーターのない建物での作業では追加料金が発生することもあるため、事前に詳細な見積もりを取得することが大切です。契約書には、作業開始のタイミングや連絡を受ける人の指定も明記しておく必要があります。
多くの業者では、年に1回程度の安否確認サービスも提供しており、独居の高齢者にとっては心強いサービスです。なお、契約内容は定期的に見直すことが推奨され、家族構成の変化や引っ越しなどがあった場合には、速やかに契約内容を更新することで、実際の作業時のトラブルを防ぐことができます。
整理した品はどう処分する?
身寄りがない、または親族に負担をかけたくないという理由で、自身の死後の遺品整理に不安を抱える人が増えています。このような場合に有効な解決策が「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対し、自己の死後の事務について生前に委任する契約です。遺品整理だけでなく葬儀や埋葬、各種行政手続きまで包括的に依頼できます。遺言と比較した場合の最大のメリットは、形式面での制約が少なく、簡易に締結できる点にあります。遺言では全文を自書する必要があるなど厳格な要式が定められていますが、死後事務委任契約は通常の契約と同様の手続きで締結可能です。
また、遺言において遺品整理に関する事項を記載しても法的効力が認められない可能性が高い一方、死後事務委任契約であれば確実な執行が期待できます。契約の受任者としては、司法書士や行政書士などの専門家、信頼できる遺品整理業者、社会福祉協議会などが選択肢となります。
費用は契約内容により異なりますが、基本的な遺品整理と諸手続きを含めて50万円から100万円程度が相場です。独身者や子供のいない夫婦、遠方に親族しかいない人にとって、死後事務委任契約は自身の最期を自分らしく締めくくるための重要な選択肢となっているのです。