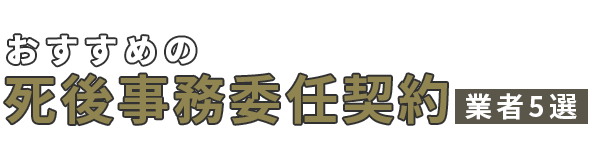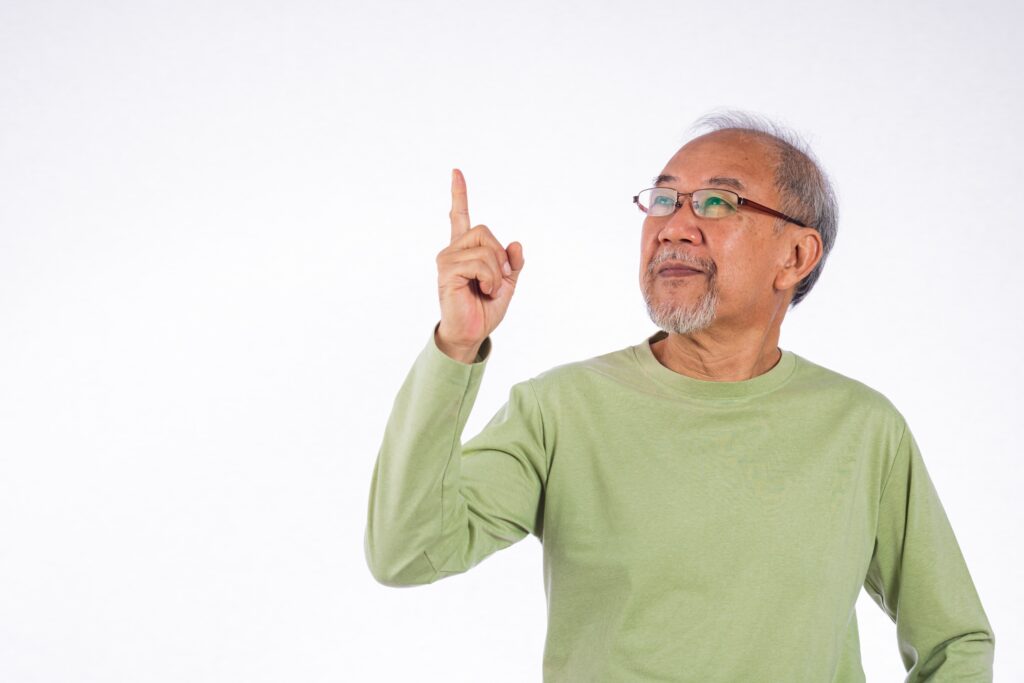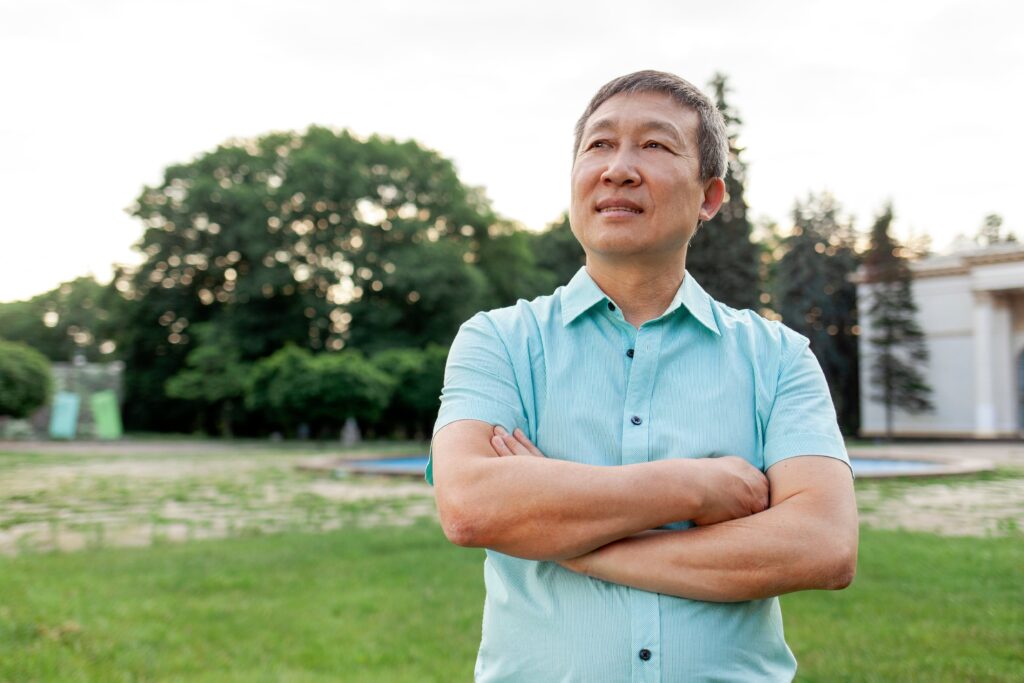自分がなくなった時のことなんてまだ先の話と思っていても、いざという時に備えて死後事務委任契約を行っておけば、残された家族にかける負担を大きく軽減できます。本記事では、死後事務委任契約とは何かについて詳しく紹介していきます。具体的な流れやできること、できないことについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
そもそも死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に行わなければいけない各種手続きを、事前に決めておいた第三者に任せられるよう生前に決めておく契約のことです。あらかじめ葬儀や火葬、遺品の整理など自分がなくなった後に発生する事務的な作業を信頼できる相手に依頼しておくことで、残された家族の負担を軽減し、安心して人生の終わりを迎える準備が行えます。ここでは、頼めることと頼める相手、遺言との違いの3つの観点から、死後事務委任契約について詳しく解説します。
頼めること
死後事務委任契約では、事務手続きはもちろん様々なことを頼めます。具体的に例を挙げると、葬儀に関する手続きや年金などの手続き、賃貸契約に関する手続き、特定の相手への死亡連絡、SNSアカウントやスマートフォンに保存しているデータの削除、サブスクリプションサービスの解約、自分が飼っていたペットの世話などです。頼みたいことはすべてできる限り細かく取り決めをして依頼することが重要です。遺言ではカバーしきれない部分を補う役割としても利用できます。
頼める相手
死後事務委任契約は、基本的に誰に頼んでも問題ありません。行政書士や弁護士、司法書士が終活サービスなどとして有料で委任者を請け負っていますが、必ずしも公的な資格を有した相手を選ぶ必要はなく、信頼できる相手であれば友人や知人、家族に頼んでも全く問題ありません。大切なのは、信頼できる相手に頼むことです。死後事務委任契約で決めるのは死後の各種手続きに関することであり、当事者である自分はすでに亡くなっています。仮に正式な契約書を結んだとしても相手が責任を全うしてくれるとは限らないからです。
友人や知人、家族に信頼できる相手がいる時はその人に、頼れる相手がいない時は有料で請け負っているサービスを活用すると良いでしょう。なお、例外として認知症を患っている方や寝たきりの方のように、契約で定められた行動がとれない状態の方には頼むことができません。
遺言との違い
死後事務委任契約も遺言もどちらも共に死後のための準備に該当しますが、目的や内容に違いがあります。一言で表すなら、遺言とは主に財産の分配や相続に関する意思を法的に残すものであり、死後事務委任契約とは葬儀や行政手続きなどの事務処理を第三者に任せるためのものです。似ているようですが役割は被っておらず、遺言ではカバー仕切れない部分を死後事務委任契約が補っています。死後事務委任契約では、相続や身分に関係する取り決めはできませんが、代わりに遺言ではできない残されたペットの世話やSNSアカウントの削除、サブスクリプションサービスの解約のような日常的な雑務まで依頼できます。
遺言と死後事務委任契約は、どちらか片方しか利用できないわけではありません。事務手続きも相続に関することも生前に決めておきたい時は、両方の制度を活用すると良いでしょう。
死後事務委任契約をするべきケース
次に死後事務委任契約をするべきケースについてまとめて紹介します。元気なうちに終活の一環で自分の死後の取り決めを行うか迷っているという方は、ぜひ参考にしてください。おひとりさま
おひとりさまで、近くに親族がいない方や、親族に迷惑をかけたくないと考えている方にとって、死後事務委任契約は心強い備えとなります。亡くなった後の手続きは多岐にわたり、誰かが対応しなければならないものですが、あらかじめ信頼できる相手に依頼しておけば、残された親族への負担を軽減できます。内縁関係のパートナーがいる人
内縁関係のパートナーがいる人も、死後事務委任契約をすることがおすすめです。なぜなら、結婚をしていない内縁関係のパートナーは、法定相続人にはなれないからです。死後事務委任契約を行っていないと、法定相続人以外の人が死後の各種事務手続きを担うことはできません。内縁関係のパートナーに事務手続きを任せたい場合は、あらかじめお互いに死後事務委任契約を結んでおくと良いでしょう。親族が高齢な人
頼れる親族がいるけれど、全員高齢で死後の手続きを任せられるか不安があるという場合には、死後事務委任契約で友人や知人などの信頼できる相手と契約を結んでおくことをおすすめします。死後の事務手続きは多岐にわたるため、高齢な方だと大きな負担に感じる可能性があります。あらかじめ信頼できる相手に依頼しておくことで、残された親族への負担を軽減できるでしょう。希望の葬送方法がある人
葬送方法とは、火葬や土葬、樹木葬、散骨などのことです。日本では火葬が一般的なため、火葬以外で希望の葬送方法がある人も死後事務委任契約をすることがおすすめです。あらかじめ希望の葬送方法を契約によって定めておかないと葬儀の手続きを行う親族の意向で、自分の希望とは異なる葬送方法が採用される可能性があります。あらかじめ話し合っておくなどの方法もありますが、より確実に希望の弔い方をしてもらうためには死後事務委任契約によって契約する方法が有効です。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約でできることをまとめて紹介します。死後事務委任契約では、主に事務手続きに関連することを依頼できます。これを頼まなければいけないといった決まった形式はなく、財産に関する事項と身分に関する事項、生前の事務に関する事項の3つに該当しないことであれば基本的に何を任せても問題ありません。葬儀に関すること
自分の葬儀に関することは、死後事務委任契約によって受託者に任せられます。具体的には、葬儀の実施方法の指定や、火葬・納骨の手配、供養の形式、遺体の引き取り、葬儀社との連絡・契約、式の規模や参列者への案内など、細かな内容まで任せることが可能です。例えば「家族葬で静かに送り出してほしい」「特定の宗教形式で供養してほしい」「遺骨はどのお墓に納めてほしい」といった希望がある場合は、事前に伝えておくことで受託者が意向に沿って対応してくれます。
特に、親族に葬儀を任せることが難しい場合や、遺体の引き取りが可能な親族がいない場合には、死後事務委任契約を活用することで、葬儀の手配が滞ることなく進められるでしょう。
葬儀に関する希望は人それぞれ異なるため、契約時にはできるだけ具体的に内容を記載しておくことが大切です。曖昧な表現では、受託者が判断に迷い、意図しない形で進んでしまう可能性もあるため、「どこで」「誰に」「どのように」といった要素を明確にしておくと安心です。
行政手続きに関すること
死後事務委任契約では、自分の仕事の行政手続きに関することも任せられます。任せられる手続きとしては、健康保険証・介護保険証の返還や年金事務局への連絡、住民税・固定資産税などの税金の納付などが挙げられます。死亡届は戸籍法によって提出可能な人が限られており、死後事務委任契約の受託者に任せることはできません。お金に関すること
死後事務委任契約では、亡くなった後に発生するお金に関する事務手続きも任せられます。例えば、賃貸住宅の契約解除、病院や介護施設の未払い費用の精算、公共料金の支払い・解約などが該当します。これらの手続きは、放置すると延滞やトラブルに繋がる可能性があるため、信頼できる相手に依頼しておくと安心です。お金に関する事務を任せたい場合は、費用の捻出方法についても事前に決めておきましょう。預貯金から支払うのか、別途準備した資金を使うのかなど、具体的な方針を契約書に明記しておくことで、受託者が迷わず対応できるようになります。
遺品の整理に関すること
死後事務委任契約では、自分の死後に残される遺品の整理も任せられます。遺品とは、亡くなった方が生前に使用していた家具や家電、衣類、書籍、日用品などを指し、これらの処分や整理は残された人にとって大きな負担となることが珍しくありません。死後事務委任契約を活用すれば、こうした遺品の整理を受託者に依頼でき、契約に基づいて適切に対応してもらうことが可能です。例えば「衣類はすべて処分してほしい」「家具はリサイクル業者に引き取ってもらいたい」「書籍は図書館に寄贈してほしい」など、具体的な希望を契約書に記載しておくことで、意図した形で整理を任せられるでしょう。
近年では、物理的な遺品だけでなく、デジタル遺品の整理を依頼するケースも増えています。デジタル遺品の整理とは、SNSアカウントの削除やパソコン・スマートフォンに保存された写真・動画・文書データの消去、クラウドサービスの解約などのことです。インターネット上に残された情報は、放置すると個人情報の流出やアカウントの乗っ取りに繋がる可能性があります。
特にSNSアカウントは、亡くなった後もプロフィールが残り続けるため、意図しない形で情報が拡散される恐れがあり、削除を依頼しておくことが望ましいです。ただし、遺品の整理を依頼する際には注意点もあります。
資産価値の高い家具や家電などは、相続の対象に該当する可能性があるため、相続人の同意なく処分してしまうと、後々トラブルになることがあります。確実に処分してもらいたい物がある場合には、契約時にその内容を明確に記載し、相続人との調整も含めて対応できるようにしておくことが重要です。
ペットに関すること
ペットと一緒に暮らしている方の中には、自分が亡くなった後、ペットがどうなってしまうのか不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。ペットは家族同然の存在であり、日々の暮らしに寄り添ってくれる大切なパートナーです。だからこそ、自分の死後にペットが安心して暮らせる環境を整えておくことは、飼い主としての責任とも言えます。遺言書は、ペットの世話や飼育に関する希望を書くことはできても、法的な拘束力がなく、実際に希望通りに実行される保証はありません。
遺言は財産の分配や法的な意思表示には有効ですが、ペットの飼育や生活に関する細かな配慮まではカバーしきれないからです。しかし、死後事務委任契約を活用すれば、ペットの飼育に関する具体的な手続きや世話を、契約に基づいて確実に実行してもらうことが可能になります。
例えば誰に引き取ってもらうのか、必要な物資や医療の手配、定期的な通院の継続など、細かい希望を契約書に記載しておくことで、ペットが安心して生活を続けられるようになります。ペットの健康状態や年齢から、自分の方が先に亡くなってしまう恐れがある時は、あらかじめペットの世話に関する内容を死後事務委任契約で決めておくと良いでしょう。
死後事務委任契約でできないこと
死後事務委任契約は様々な事務を任せられますが、財産と身分、生前の事務に関することは任せられません。ここでは、死後事務委任契約でできないことをまとめて紹介します。身分に関する事項
死後事務委任契約では、身分に関する事項も依頼できません。身分行為は本人の意思と人格に関わる行為だからです。身分に関する事項には、結婚や離婚、養子縁組、子供の認知などが該当します。生前の事務に関する事項
死後事務委任契約は、自分の死後の事務などを特定の相手に任せるための制度です。そのため、自分の生前の事務に関することは任せられません。自分が加齢によって認知症や判断能力が低下した際に財産の管理や身の回りのこと、介護、生活の補助などを任せたい相手がいる場合は、死後事務委任契約ではなく後見制度などを活用すると良いでしょう。後見制度は、本人の生前における支援を目的としているため、死後事務委任契約とは役割が明確に異なります。死後事務委任契約と後見制度は、どちらも人生の終盤に備えるための大切な手段ですが、対象となる時期や内容が異なるので、目的に応じて使い分けることが重要です。
自分が亡くなった後の事務手続きを誰かに任せたい場合は死後事務委任契約を、生きている間の生活支援や財産管理を任せたい場合は後見制度を選ぶと良いでしょう。
相続の手続き
死亡後の手続きとして相続の手続きを思い浮かべる方は少なくないかと思います。しかし、死後事務委任契約では、遺産の分割方法の指定や預金口座の解約、相続登記といった相続に関する手続きを依頼することはできません。相続の手続きは、相続人全員の合意と遺言内容で決まるからです。医療同意を依頼できない
死後事務委任契約では、医療同意を依頼できません。医療同意は、当事者である本人やその家族のみが行える行為だからです。死後事務委任契約を頼んだ相手が医師から十分な説明を受けたとしても、医療同意はできない点に注意が必要です。死後事務委任契約の流れ
最後に死後事務委任契約を結ぶ、具体的な流れを紹介します。ステップごとに分けて解説するので、今後死後事務委任契約を検討している方は、ぜひ参考にしてください。家族や友人のように親しい間柄の相手に頼む場合、人によっては面倒な手続きを行わず口約束だけで済ませたいと感じる方もいるかもしれません。しかし、口約束で済ませてしまうと、何をどこまで頼んだのか記録が残らないことから約束が曖昧になる恐れがあります。面倒だったとしても必ず処理・実行してほしいことは、正式に契約を結んで頼んでおくことをおすすめします。
事前に準備することの確認
死後事務委任契約を行うと決めた時に、まず最初に取り組むべきなのが、契約に向けた事前準備の確認です。正式な契約手続きを進める際には、必要な情報や書類がすべて揃っていることが前提となるため、焦らず丁寧に準備を整えることが、スムーズな契約につながります。準備の内容としては、まず「何を任せたいのか」を明確にすることが重要です。亡くなった後に必要となる事務手続きは人によって異なるため、自分自身の生活環境や希望に合わせて、依頼したい内容を具体的にリストアップしておきましょう。次に、その業務を誰に任せるかを検討します。
依頼する相手が決まったら、報酬の有無や金額についても話し合い、費用面の整理をしなければなりません。なお、これらの準備は必ずしも決まった順番で進める必要はありません。自分のペースで、一つひとつ丁寧に取り組むことが大切です。
任せたい内容をリストアップ
事前に準備するべきことを確認したら、まずは任せたい内容をリストアップすることがおすすめです。任せたい内容次第で、死後事務委任契約を任せるべき適任は変わるからです。死後事務委任契約では、主に遺言では頼めない事務的な作業を受託者に任せられます。決まった形式はなく、財産に関する事項と身分に関する事項、生前の事務に関する事項の3つに該当しないことであれば何を任せても基本的に問題ありません。一般的には、自分の葬儀をどのような形で実施してほしい、役所の手続きを任せたい、自分の死後ペットの世話をしてほしい、友人のAさんBさんに自分がなくなったことを連絡してほしいといった内容などを決めます。
頼む内容を決定する際は、必ず細かく決めることが大切です。例えば「親しかった友人に連絡してほしい」ではなく「東京に住むAさんと北海道に住むBさんに、自分がなくなったという内容の手紙を送ってほしい」などのようにできる限り明確に決めましょう。
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に効力を発揮する契約です。曖昧な指示では、思っていた形とは異なる対応がされてしまう恐れもあります。任せたい内容は丁寧に言語化し、受託者が迷わず実行できるようにしておかなければなりません。
任せる相手を検討する
任せたい内容のリストアップが完了したら、次に考えるべきことは誰に任せるのかという点です。死後事務委任契約は、家族や親しい友人、知人、弁護士・行政書士などの専門家、終活を支援する団体など、さまざまな相手に依頼できます。法的には誰に頼んでも問題ありませんが、実際に事務作業を遂行するのは自分の死後であるため、確実に対応してもらえるかどうかを慎重に見極める必要があります。例えば、病気を抱えている方や体力的に不安のある方、遠方に住んでいる方は、契約後に実行が困難になる可能性があるため、避けた方が無難です。
また、よくある失敗例として、自分よりも高齢な家族に頼んでしまうケースが挙げられます。両親や兄弟姉妹など自分よりも年齢が高い方に任せると、実行時にすでに高齢であったり、先に亡くなってしまっていたりする可能性もあるので、注意が必要です。
仕事や家庭の事情で忙しい人に頼むことも避けることをおすすめします。なぜなら頼んでおいた作業の対応が遅れたり、十分な時間を割いてもらえない可能性があったりするからです。年齢制限などの法的な制約はありませんが、任せる相手の健康状態や生活状況、責任感などを総合的に判断し、長期的に信頼できるかどうかを基準に選ぶことが大切です。
専門家への相談には費用が発生しますが、業務の確実性や安心感を得られるというメリットがあります。身近な人に依頼する場合は、事前にしっかりと話し合い、依頼したいことを詳細に共有しておくことで、よりスムーズな実行に繋げられます。
費用を決める
任せたい内容と相手が決まったら、次に費用を決めましょう。死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に実行される契約のため、費用に関する取り決めを事前に明確にしておくことが、後々のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。費用は自分だけで決めるのではなく、契約を結ぶ相手としっかり相談をしながら決めることが基本です。相手の負担や状況を考慮し、双方納得の上で決定することが信頼関係の維持に繋がります。費用の取り決めには、大きく分けて2つの視点があります。1つは、頼みごとを遂行するためにかかる実費をどこから支払うのかという点です。
例えば、葬儀の手配や火葬費用、公共料金の解約に伴う支払い、住居の片付けにかかる費用など、実際の作業にはさまざまな経費が発生する可能性があります。これらの費用を、預貯金から支払うのか、別途用意した資金からあてるのか、家族に負担してもらうのかなど、支払いの方法を事前に決めておくことで、受託者が迷わず対応できるようになります。
もう1つは、報酬の有無についてです。友人や知人、家族に依頼する場合は、報酬を支払わないケースも多く見られますが、だからといって何も取り決めをしないまま契約を進めることは避けた方が無難です。報酬を支払わない場合でも「報酬はなし」と契約書に明記しておくことで、後々の誤解や揉め事を予防できます。
必要書類を集める
公証役場などで死後事務委任契約の契約書を作成する際には、依頼する人と依頼される人それぞれの印鑑証明書と実印、身分証明書を用意する必要があります。身分証明書としては、マイナンバーカードや運転免許証、住民基本台帳カードなどを用意すると良いでしょう。必要書類が揃っていないと依頼したい内容などが明確に決まっていても正式な契約書作成を依頼することはできないので注意してください。契約書の作成は必須ではありませんが、知人や友人、家族に頼む場合でも契約書として正式な書面を作成することをおすすめします。
口頭で頼んだ際には約束してもらえても、時間の経過で依頼内容の認識にズレが発生したり、頼んだこと自体を忘れられたりする可能性が考えられますが、契約書として書類に残しておけばトラブルの発生を予防できます。なお、印鑑証明書は必ず3か月以内に発行されたものを用意しなければなりません。