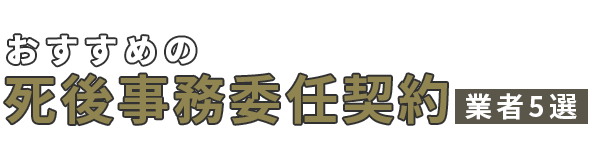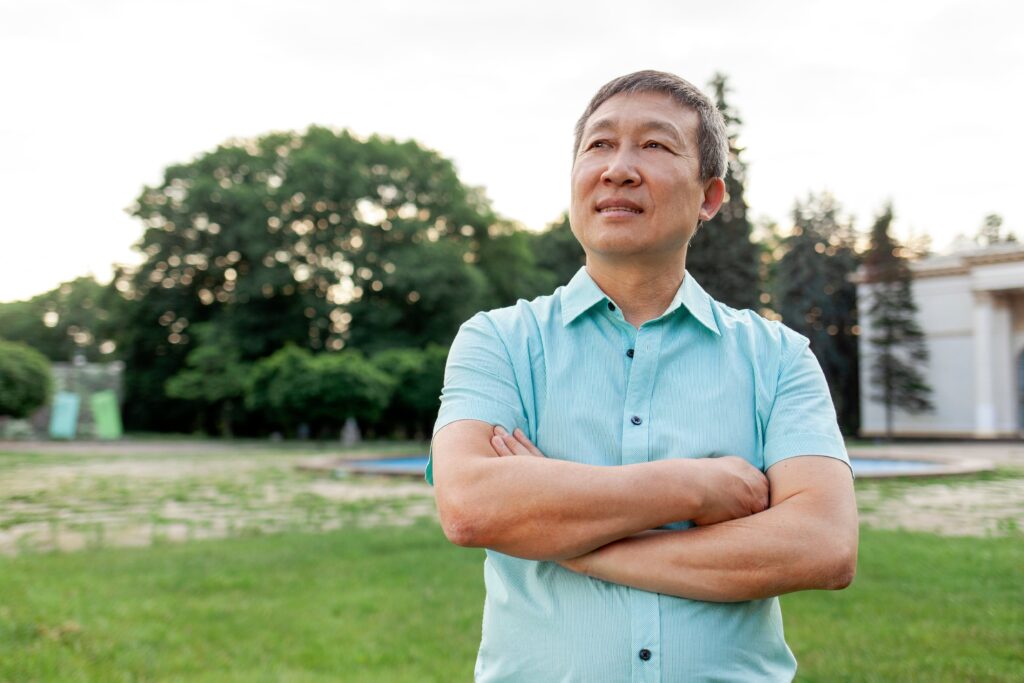
近年、ひとりで老後を迎える人が増えています。自分のペースで暮らせる一方で、経済的な心配や健康、亡くなった後の手続きなど、将来への不安を抱える方も少なくありません。この記事では、おひとりさまが老後に抱えやすい3つの不安と、それを解消するための具体的な方法をわかりやすく紹介します。
おひとりさまが抱えがちな3つの不安
老後を一人で過ごすことには、自分のペースで暮らせる自由がありますが、その一方で誰もが少なからず不安を抱えます。代表的なものがお金、健康、死後のことに関する3つの悩みです。ここでは、それぞれの不安の実態と背景を整理し、なぜ対策が必要なのかを明確にしていきます。経済的な不安
老後のおひとりさまがもっとも感じやすいのが、年金だけで生活できるかという経済的な不安です。総務省の統計では、65歳以上の単身無職世帯は毎月およそ3万円の赤字とされており、退職金や貯蓄を取り崩す生活が現実です。長生きすればするほど資金不足のリスクは高まります。急な病気や介護が必要になった場合、想定外の出費も発生します。さらに、家族と暮らす場合より固定費が割高になる傾向もあり、家賃や光熱費が大きな負担となります。こうした背景から、早い段階で年金額の確認や資産運用を始めることが重要です。
参考元:セゾンのくらし大研究 シニア
健康・介護への不安
体力や免疫力が落ちる高齢期には、病気の早期発見や適切な治療が遅れるリスクがあります。とくにおひとりさまの場合、自分自身の体調変化に気付けない場合もあり、病気の発覚が遅れるケースが多いです。また、入院時には身元保証人が求められることがあり、頼れる家族がいない場合は手続きそのものが進められないこともあります。さらに、通院や介護が必要になった際には、生活を支える人手も不足しがちです。実情を踏まえると、日頃から健康維持に努めるとともに、かかりつけ医をもつことや介護サービスの利用を検討するなど、早めの備えが安心につながります。
死後の手続き・孤独への不安
亡くなった後、誰が葬儀や遺品整理をしてくれるのかという不安も、おひとりさまにとって切実な問題です。近年では孤独死が社会問題化しており、発見までに時間がかかるケースも少なくありません。身寄りがいない場合、行政が火葬を行いますが、本人の意思が反映されないことも多いのが現実です。また、残された財産の整理や相続の手続きをしておかないと、希望する相続先に渡らず、国庫に帰属してしまうこともあります。こうした事態を防ぐには、生前に死後事務委任契約や遺言書を作成しておくことが欠かせません。自分の人生の最期を自分で設計する意識が、安心した老後につながります。
おひとりさまで迎える老後を快適にするための6つの対策
老後の不安は誰にでも起こりうるものです。しかし、正しい準備と知識があれば、その不安を大きく軽減できます。ここでは、経済面・健康面・死後の備えまで、おひとりさまが安心して老後を過ごすための6つの実践的な方法を紹介します。資金計画と資産運用を見直す
老後の安心を支える第一歩は、現実的な資金計画を立てることです。ねんきん定期便などで将来の年金受給額を確認し、生活費や医療費などを含めた収支シミュレーションを行いましょう。不足分が見込まれる場合は、固定費の削減や積立投資・NISAなどを活用した資産運用で補うのが有効です。とくにおひとりさまは、急な出費に備えて生活費の半年分程度を現金で確保し、それ以外を長期投資に回すと安心です。早めに計画を立てることで、将来の不安を数字で見える化することで、心の余裕をもてます。
見守りサービスや地域コミュニティを活用する
一人暮らしでも孤立しないためには、人とのつながりをもつことが欠かせません。自治体や郵便局などが行う見守りサービスを利用すれば、定期的な安否確認や緊急時の対応が受けられます。また、地域のサロンや趣味サークルなどのコミュニティに参加することで、生活にハリが生まれ、認知症予防にもつながります。人と関わる習慣をもつことは、孤独死のリスクを減らすもっとも効果的な対策のひとつです。
身元保証・死後事務委任契約を早めに検討
おひとりさまの老後では、入院や施設入所時に身元保証人が必要になる場面が多くあります。身近に頼れる人がいない場合は、専門の身元保証サービスや死後事務委任契約を検討しましょう。死後事務委任契約は、葬儀や遺品整理、各種解約手続きを第三者に託せる制度で、専門家や法人に依頼できます。費用はかかりますが、確実に希望を叶えられる点で安心です。生前から信頼できる相手を選び、契約内容を明確にしておくことが大切です。
健康維持と生活習慣の管理を徹底
体調を崩さないためには、日々の健康管理が欠かせません。バランスのよい食事、軽い運動、十分な睡眠を基本に、定期的な健康診断を受けておくことが大切です。とくにおひとりさまは、通院や服薬の管理を自分で行う必要があるため、スケジュール管理アプリや服薬カレンダーなどを活用しましょう。また、かかりつけ医を決めておけば、体調変化にすぐ対応してもらえる安心感があります。