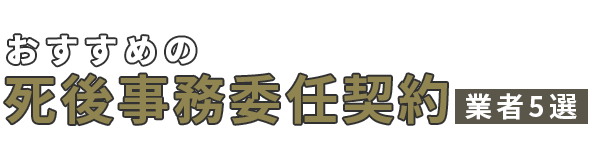家族が亡くなった際に、どのような手続きが必要になるのか分からず悩む方も多いでしょう。死亡届や役所での手続きなど、対応すべき項目は多岐にわたります。この記事では、亡くなったあとに必要な手続きを時系列で紹介します。事前に理解しておくことで、スムーズに手続きを進められ、負担を軽減できるでしょう。
死亡当日にするべき手続き
死亡した当日でも、家族や親族は速やかに対応すべきことがいくつかあります。悲しみの中で慌てることのないよう、ポイントを押さえながら順序立てて進めることが大切です。死亡診断書の受け取りとコピー
主治医が発行する死亡診断書は、今後の手続きで必ず必要になります。家族や親族が受け取り、必要に応じて複数枚コピーを取って保管します。医師が死亡診断書を発行できない場合は死体検案書を受け取ります。法律上、誰が受け取るかの優先順位は定められていませんが、故人にもっとも身近で関係の深い親族が受け取ることが一般的です。
近親者への連絡
親族や勤務先、近所の方々へ、亡くなった事実を伝えます。連絡漏れを防ぐため、事前に連絡者リストを作成しておくと便利です。通夜や葬儀の日取りがすでに確定している場合は、スケジュールの情報も合わせて伝えると参列者が準備しやすくなります。葬儀社の選定
葬儀社を選ぶ前に、故人の希望があったかを確認しましょう。生前に希望を聞いていない場合は、遺言書やエンディングノートに記載されていることもあります。葬儀の形式を決め、自分たちに合った葬儀社を選びます。詳細まで決める余裕がない場合は、まずは搬送のみ対応してくれる葬儀社に依頼することも可能です。病院によっては提携葬儀社を紹介してくれる場合もあり、搬送から法要までまとめて依頼できるプランがあります。
遺体の搬送と退院手続き
病院で亡くなった場合、自宅や葬儀社の安置場へ遺体を搬送します。同時に入院費の清算や退院手続きを行います。費用の支払い方法や順序を事前に家族で話し合っておくと、のちのトラブルを避けられるでしょう。通夜・葬儀・火葬に際して行う手続き
葬儀は、通夜から葬儀・火葬まで複数の手続きや準備を順に進める必要があります。喪主や家族は、葬儀社と連携しながら落ち着いて対応することが大切です。通夜
通夜は通常、葬儀社を通して行われますが、地域の風習や家族の希望に応じて調整することもあります。葬儀社が主導する場合、祭壇の手配や会場準備、参列者への案内などは担当者が対応します。家族の役割は、喪主を決め、参列者の出迎えや代表挨拶、見送りなどを行うのが一般的です。通夜終了後は、翌日の葬儀について葬儀社と確認を行います。
葬儀
葬儀当日は、葬儀社が全体の進行を取り仕切りますが、家族や地域の慣習に従いながら進める場合もあります。喪主や受付係の役割分担、席次や焼香の順序、祭壇や会場設営、弔電の管理などを葬儀社と確認しておきましょう。葬儀の日程は通常、亡くなった翌日または翌々日ですが、会場や参列者の都合により多少調整されることもあります。
火葬
葬儀後、棺を霊柩車に乗せて火葬場に搬送します。その際、火葬許可証を必ず持参します。そのほかの家族は自家用車やタクシーで移動し、必要に応じて交通手段を事前に調整しましょう。火葬は通常1時間程度で終了します。待機中に今後の法要日程などを話し合うことも可能です。火葬済証明の取得
火葬後、遺骨を骨壺に収めたうえで火葬許可証に押印された火葬済証明を受け取ります。納骨の際に必要となるため、自宅で保管しておきましょう。万が一紛失した場合に備えてコピーを取っておくと安心です。葬儀後の手続き
葬儀を終えた後は、費用の精算や書類の受け取りなど、いくつかの手続きを行う必要があります。葬儀代は相続や葬祭費の申請にも関わる重要な項目であり、正確に処理することが重要です。葬儀代の支払い
葬儀が終わると、通常は1週間前後で葬儀社から請求書が届きます。この請求書をもとに、葬儀代を支払います。葬儀社によっては葬儀当日に支払う場合や現金で直接手渡しするケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。高額になることが多いため、支払い方法やタイミングを家族で把握しておきましょう。また、葬儀代を故人の口座から支払いたい場合は注意が必要です。
故人が死亡した旨を銀行に届け出ると、その預金口座を相続手続きが終わるまで引き出せないか、制限されるケースがあります。故人の預金は相続財産にあたるため、相続人全員に支払うことを伝え、了承を得ることが必要です。事前に話し合っておくことで、のちのトラブルを防げます。
葬儀代の領収書の取得
葬儀代の支払いを済ませたあとは、葬儀社から正式な領収書を必ず受け取って保管しておきます。この領収書は葬祭費の支給申請や相続手続きに必要となる重要な書類です。紛失しないよう大切に保管し、必要な場合にすぐ提出できるよう整理しておきましょう。役所での諸手続き
家族が亡くなった後、役所や年金事務所、警察署で行う手続きがあります。期限が定められている手続きもあるため、10日目を目安にまとめて対応するとスムーズです。故人の本籍地の役所で行う手続き
本籍地の役所では、除籍謄本を取得します。除籍謄本には死亡の事実が記載され、相続手続きや法定相続人の確認に必要です。可能であれば、出生から死亡までの戸籍や相続人全員の現在戸籍もあわせて取得しておくと手続きがスムーズに進められます。取得は窓口で直接行うか郵送請求が可能です。銀行などで提出する場合に返却されないこともあるため、コピーを2~3枚用意しておくと安心です。
故人の住所地の役所で行う手続き
住所地の役所では、複数の窓口で手続きを行います。戸籍・住民票担当では住民票の除票を取得、国民健康保険担当や後期高齢者医療担当では健康保険証の返還・資格喪失届の提出・葬祭費や高額療養費の申請用紙の取得を行います。必要に応じて障がい担当で手続きも進めましょう。手続き期限は7日から14日以内ですが、過ぎても罰則はありませんが、忌引き期間中に対応するとよいでしょう。事前に書類を確認して準備しておくと効率的です。
最寄りの年金事務所で行う手続き
年金事務所では、年金受給者死亡届の提出、未支給年金の請求、遺族年金の請求を行います。受給状況により必要な手続きや書類が異なるため、事前に電話で基礎年金番号やマイナンバーを伝え、必要書類を確認しておくとスムーズです。窓口か郵送で手続きを進めますが、状況に応じて案内を受けながら進めていくと安心です。最寄りの警察署での手続き
故人が運転免許証を所持していた場合は警察署で返還手続きを行います。死亡診断書のコピーを持参すると手続きがスムーズです。返還せずに手元に置いておく場合でも罰則はありません。誰が返却に行くのか事前に相談しておくとよいでしょう。在職中に亡くなった場合の手続き
勤務中に亡くなった場合は、会社を通して健康保険や年金などの手続きを進めることが一般的です。死亡の連絡を入れる際に、必要な手続きについて案内してもらうと、漏れなく進められます。加えて、退職金や未払いの給与、各種手当などの清算もあわせて確認しておくと安心です。会社に相談して、必要な書類や手続きの流れを整理しておくことが大切です。
故人の諸契約の解約手続き
故人が亡くなった後は、役所や年金の手続きを終えたあとに公共料金や各種契約の手続きを進める必要があります。過払い金や未払い金などお金のやり取りが関わるため、なるべく早く対応しておきましょう。契約の解約か名義変更かによって手続き内容が異なるため、家族で事前に方針を決めておくと安心です。まずは契約先に死亡を連絡し、不要な支払いが発生しないよう確認しましょう。
公共料金の解約や名義変更
電気、ガス、水道などの公共料金は、契約先に連絡して解約または名義変更を行います。請求書や利用明細に問い合わせ先の情報が記載されていることが多いですが、不明な場合は住所地に近い会社へ確認します。近年は電力やガスの自由化により、契約先が異なることもあるため注意が必要です。水道は住所地の水道局に連絡します。引き落とし口座の通帳で確認すると、手続きがスムーズに進みます。
電話、インターネット、テレビ等の解約や名義変更
契約先を確認し、死亡を連絡したうえで指示に従って手続きを進めます。固定電話やインターネットはモデムやルーターの返却や立ち合いが必要な場合もあり、紛失すると料金が発生する場合もあります。携帯電話は店舗やWebで手続きを進め、NHKは管轄のふれあいセンターに連絡して解約や名義変更を行いましょう。解約時に過払いが発生することもあるため、返金の有無もあわせて確認しておくと安心です。
生命保険の手続き
生命保険の保険証券や契約内容通知を確認し、死亡保険金の請求を進めます。手続きは契約者や被保険者、保険金受取人に基づき行いましょう。保険金の支払いまでに2~3か月かかることもあるため、早めに対応することが必要です。入院給付金の請求も相続財産として扱われ、相続人が確定してから受け取るため、死亡保険金の手続きとは区別して進める必要があります。故人の契約先の種類や状況によって手続き方法は異なるため、早めに対応することで不要な支払いを防ぎ、トラブルを避けられます。
遺産相続に関する手続き
遺産相続手続きは、故人の遺産や権利を相続人が受け継ぐための手続きです。まず遺言書の有無を確認し、相続人を確定します。相続人の確定には戸籍謄本などの書類が必要です。その後、現金、不動産、株式、車、生命保険などの相続財産を調査し、評価額を把握します。その後、相続方法を決定し、相続または放棄の選択を行いましょう。必要に応じて遺産分割協議書を作成し、相続税の申告や納付を進めます。
最後に相続遺産の分配や名義変更を行います。各手続きには期限があるため、早めに対応しましょう。相続手続きには実印や印鑑証明書が必要な場合も多いため、事前に準備をしておくことでスムーズに進められます。